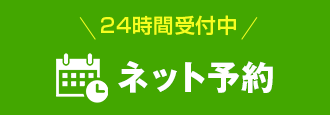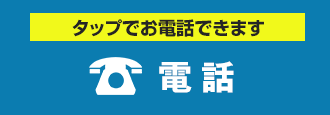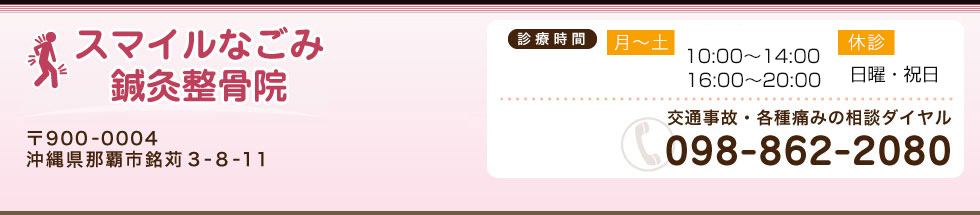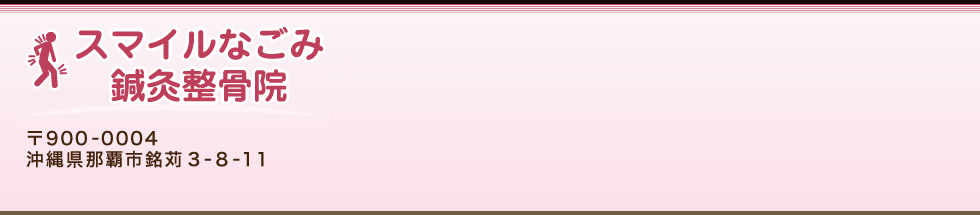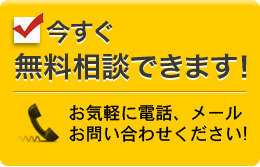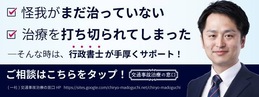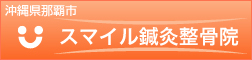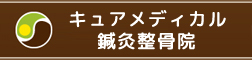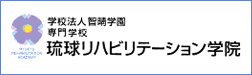サッカー
生徒も保護者も指導者の皆さんも、ちょっとした痛みや違和感、フォームの乱れなど「小さなサイン」を見逃さず、スポーツ障害を予防しましょう。
スポーツ障害とは
スポーツで生じる身体の故障には、瞬間的な外力によって起こる「スポーツ外傷」(骨折、脱臼、捻挫など)と、身体に過度の負担が繰り返しかかることによって、痛みなどの症状が慢性的に現れる「スポーツ障害」があります。
スポーツ障害は早期に対処しないと重症化して、関節が変形したり骨が分離したまま直らなかったりと、日常生活に支障を生じることがあります。
ただし、厳密に区別せず、スポーツ外傷とスポーツ障害を総称してスポーツ障害と呼ぶ場合もあります。

バスケットボール

【骨や筋肉の成長時期のピーク】
| 身長(骨) |
13.45歳 |
| 筋肉 |
13.75歳 |
| 骨量 |
14.11歳 |
中高生にスポーツ障害が起こる理由
成長期にはまず骨が成長し、筋肉がそれを追いかけるように身体が作られていきます。
男子の場合は高校1~2年生、女子は中学3年生ほどまでが成長期です。この時期の骨は、両端が軟骨になっていて、骨端線と呼ばれる部分から骨が伸びていきます。
そのため、骨、関節は成人と違って構造的に弱く、強いけん引力、圧迫力が繰り返し働くと、傷ついたり変形したりして障害が生じやすいのが特徴です。
【成長期の骨の構造】
主なスポーツ障害
中高生のスポーツでは野球が盛んですが、野球選手には投げ過ぎによる肘の障害である、野球肘が特に多く見られます。
野球肘には、肘の内側に発生する内側側副靭帯損傷(内側型野球肘)と、肘の外側に発生する離脱性骨軟骨炎(外側型野球肘)の2種類があります。
走ったりジャンプしたりするスポーツでは、膝蓋(しつがい)靭帯が脛骨(けいこつ)付着部からはがれて骨が出っ張るオスグッド・シュラッター病の発症率が高いです。
前十字靭帯損傷も非常に多く、特に女子の場合はX脚が原因となるので、普段の姿勢から気をつけましょう。
【野球肘】
【オスグッド・シュラッター病】
【前十字靭帯損傷】
ポイント1
ウォームアップ
スポーツによる障害や外傷を未然に防ぐためには、準備運動が欠かせません。
体温・代謝を上げ、関節を柔軟にするなどの効果があります。
15~20分ほど、ストレッチやジョギングなどをして身体を温めましょう。
動作に勢いをつけるのではなく、ゆっくり筋肉を伸ばすように行うことがコツです。
ポイント2
クールダウン
ウォームアップと反対の効果を持つクールダウン(整理運動)は、運動によって興奮した身体を鎮めて、疲労回復を促す効果があります。
急激に運動を停止すると身体によくありません。
軽いジョギングやウォーキングなど、徐々に動きを止め、ストレッチやアイシングを行いましょう。
ポイント3
適度な練習
一定の動作を繰り返し行うことで関節、筋肉、腱などに継続的に負担が加わります。
スポーツ障害は、オーバーユース(使いすぎ)によって起こることがほとんどです。
例えば、野球の全力投球は、中学生なら1日70球までで週350球。高校生なら1日100球までで週500球が限度です。
ポイント4
体格に応じた練習
中高生の時期は成長スピードや体格の個人差が大きいです。
指導者は、年齢ではなく個人の発育に合わせた指導をするよう気をつけましょう。
筋力トレーニングは、筋肉が増えた時期に行わないと意味がありません。
身体ができていないうちは、瞬発性を養ったり身体の使い方を覚えたりしましょう。
小さなサインを見逃さないようにしましょう。
痛みを感じたら病院を受診するのが一番ですが、気づかないうちに障害が進んでいることがあります。
例えば、投球フォームで肘が下がってきたら、肘に障害が起こっているかもしれません。
また、膝の下を押さえてみて痛むようならオスグッド・シュラッター病かもしれません。
我慢して続けていると、将来障害が残ることがあるので、指導者や家族は注意深く見守ることが大切です。
「痛い」と言えない…?
「痛み」はスポーツ障害の重要なサインですが、「痛い」と言ったり練習を休んだりすると試合に出してもらえないと思い、無理して練習を続ける子どもがいます。